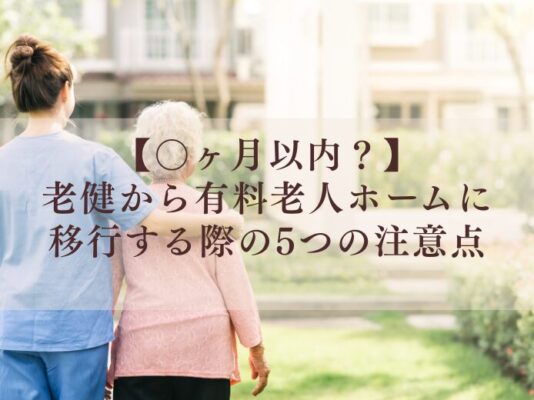【○ヶ月以内?】老健から有料老人ホームに移行する際の5つの注意点

「そろそろ老健の退所が近づいてきたけれど、この先どうすればいいの?」
そんな不安を抱えるご家族は少なくありません。
そもそも種類の施設いろんながあって、違いや移行の手順なんかもわかりづらいですよね。
ただ、全容を把握せずに決めてしまうとあとで後悔することも…。
そこで本記事では、介護老人保健施設(老健)と有料老人ホームの違いからそれぞれのメリット・デメリット、費用・サービス内容の比較や、有料老人ホームへのスムーズな移行方法までをわかりやすく解説します。
介護老人保健施設と有料老人ホームの違い
高齢者の暮らしを支える施設にはさまざまな種類がありますが、これらは目的やサービス内容が異なるため、利用者や家族にとって重要な選択ポイントとなります。
この2つの施設は、目的や提供されるサービスが異なるため、それぞれに適した利用者像があります。
この記事では、両者の違いを明らかにし、それぞれ以下の10項目に分けて詳しく紹介していきます。
①特徴
②費用
③入居対象者
④リハビリ
⑤医療体制
⑥介護
⑦食事
⑧居室・設備面
⑨入居期間
⑩3か月ルール
①特徴
以下の内容ではそれぞれの施設の特徴について解説していきます。
【介護老人保健施設】 主に自治体や政府などの公共団体が運営し、医療と介護を融合させた施設です。
リハビリを通じて利用者の在宅復帰を目的としています。
医師や看護師が常駐し、医療ケアとリハビリの提供が充実しています。
比較的短期間の利用を前提としており、公的施設のため初期費用がかからず、月額費用も民間施設と比較して手頃です。
【有料老人ホーム】 民間施設で企業や個人が運営し、より多様なサービスや快適性を追求する傾向があり、利用者のニーズに応じた柔軟な対応が特徴です。
長期的な生活を送る場としての施設とされています。
介護付き住宅型や健康型といった種類があり、介護サービスを受けながら自由な暮らしを楽しむことができます。
②費用
介護老人保健施設と有料老人ホームは、その目的やサービス内容だけでなく、費用にも大きな違いがあります。
特に、初期費用や月額利用料の違いは知っておきたいポイントです。
以下の内容では、それぞれの費用について解説します。
初期費用(入居一時金)
【介護老人保健施設】
比較的負担が少なく初期費用が不要です。
契約時にまとまった金額を支払う必要がありません。
【有料老人ホーム】
主に家賃の前払いとして支払う費用です。
施設によって数十万円から数千万円まで、幅広い金額が設定されています。
初期費用を支払う必要があるかが異なるため、確認が必要です。
月額利用料(内訳例:居住費、食費、介護サービス費)
【介護老人保健施設】
相部屋の場合: 約7~10万円
個室の場合: 約18~22万円 (地域や施設の設備によって異なります)
【有料老人ホーム】
介護付き有料老人ホームの場合:平均月額は約15~35万円ほどです。
住宅型有料老人ホームの場合:約12~30万円ほどが相場です。
また、月額費用以外にもオムツ利用料金、日用品なども月々の負担となります。
そのような詳細は各施設、異なるため、施設見学や問い合わせ等、事前に調べることをおすすめします。
③入居対象者
①の特徴でも述べたように、介護老人保健施設ではリハビリを必要とする高齢者が主な対象であり、有料老人ホームは、日常生活のサポートや快適な暮らしを求める高齢者が対象となる施設です。
以下では具体的な年齢や介護度、身体状況について紹介します。
【介護老人保健施設】
65歳以上で要介護1以上の認定を受けた方が基本となります。
40歳~64歳でも、初老期における認知症や特定の疾患がある場合は利用が可能となります。
介護が不要な健康な高齢者から、軽度の介護が必要な方まで幅広く受け入れの対応を行っている。
【有料老人ホーム】
施設によって異なりますが、60歳以上の方が対象となります。
また、自立されている方から要支援、要介護まで幅広くまた、認知症の方でも入居可能な施設が多数あります。
施設によって対応範囲が異なるため、事前に施設へ確認することをおすすめします。
④リハビリ
施設によってリハビリの内容や体制、目的に違いがあり、以下の内容ではそれぞれ詳しく解説していきます。
【介護老人保健施設】
入居者が自宅に戻れるように集中的なリハビリ、すなわち回復を目指します。
専門職員が入居者の身体状態を評価し、それに基づいた個別のリハビリプログラムを作成するため、一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなケアが行われています。
理学療法士による訓練
主に身体機能の回復・維持を目的とします。
【内容】
・屋内、屋外の歩行訓練
・筋力強化訓練
・関節の可動域訓練、バランス訓練
筋力、関節の動き、平衡感覚を鍛えることで、身体全体の調整力が向上します。
片足立ちやゆっくりした動作を取り入れるトレーニングが一般的です。
作業療法士による訓練
心身の機能回復や生活の質向上を目的としています。訓練は、主に次のような分野に分けられます。
【内容】
・身体的リハビリテーション
筋力や関節の動きを改善し、食事や着替え、入浴など、日常生活動作の支援を行います。
・精神的リハビリテーション
家事や趣味などの「作業」を通じて心の健康を維持・向上させる。
・老年期リハビリテーション
高齢者が自立した生活を送れるよう支援し、機能低下防止のリハビリが行われます。
・言語聴覚療法による訓練
発声・発度訓練、誤嚥防止のための嚥下訓練を行い、コミュニケーション能力の回復を目指します。
【有料老人ホーム】
入居者が心身ともに自立した生活を送るための支援を目的としています。
専門職である機能訓練指導員が中心となり、個別に設定されたケアプランに基づき、生活場面での自然な動作を活用したリハビリが特徴です。
また、日常的な動作やレクリエーションを通じて、心身の機能維持や向上が期待されます。
⑤医療体制
以下では医療体制について比較し解説していきます。
【老人介護保険施設】
施設には医師・看護師が常勤しており、病状が安定している人であれば、点滴・褥瘡処置・服薬管理・慢性疾患の経過観察など、比較的しっかりした医療対応が受けられます。
退院後すぐのケアや、在宅復帰を前提とした支援に向いています。
【有料老人ホーム】
医療行為の範囲は限られているのが一般的です。
常駐しているのは介護スタッフが中心となり、看護師も常駐している施設もありますが、医師は外部からの訪問のみという場合もあります。
医療依存度の高い方、たとえば、胃ろう、人工呼吸器、頻繁な点滴などには対応できないケースもあるため、事前の確認が重要です。
⑥介護
それぞれの介護の違いについて紹介していきます。
【介護老人保健施設】
食事や入浴、排せつなどの基本的な介助に加え、リハビリスタッフによる機能回復訓練が日常的に行われます。
介護というより「医療とリハビリの支援がついた生活介助」が中心となっています。
【有料老人ホーム】
日常生活を快適に送るための介護が中心となります。
食事や入浴の介助はもちろん、レクリエーションや趣味活動などの生活の質を高めるサポートに力を入れている施設も多くあります。
⑦食事
介護老人保健施設では特に医療的な側面が強く、病状に応じた栄養素の計算が必要です。
たとえば、嚥下困難がある方には特殊な食形態が用意されます。
栄養管理は医師や管理栄養士が主導で進行し、リハビリの進行に合わせた食事内容の見直しが行われます。
有料老人ホームでは、快適で安心できる生活環境を提供しながら、利用者の健康維持をサポートします。
管理栄養士による献立作成が主流ですが、施設によっては行事のイベント食を提供を行っているところもあります。
⑧居室・設備面
【介護老人保健施設】 医療ケアやリハビリを重視した設備が特徴です。
居室は多くの場合簡素で、必要最低限の家具が備えられています。
リハビリ室や医療機器が充実しており、入居者が効率的にリハビリを受けられる環境が整っています。
共同スペースが多く、入居者同士の取りやすい仕組みになっています。
【 有料老人ホーム】 長期的な住まいとして快適さを重視した居室が整備されています。
個室タイプが一般的で、入居者が好きな家具を持ち込むことも可能です。
施設によってはレクリエーションスペースや庭園、カフェテリアなど、リラックスできる設備が充実しています。
⑨入所期間
介護老人保健施設では原則として3~6か月の短期利用が基本です。
リハビリを終えた後、在宅復帰を目指すため、長期間の入所は想定されていないことが多いです。
必要に応じて期間延長も可能ですが、長期利用を目的とした施設ではありません。
有料老人ホームは基本的に長期的な利用が可能で、終身利用を前提とした施設が多いです。
終の住まいとして選ぶことが一般的で、安心して住み続けられる環境が整っています。
住み替えが必要になるケースは少なく、利用者のライフスタイルに寄り添う形となっております。
⑩三か月ルール
介護老人保健施設の三か月ルールは、利用者が一定期間ごとに退所の可能性を検討される制度です。
このルールの背景には、介護老人保険施設の目的である「在宅復帰支援」が強く反映されています。
たとえば、回復状況や介護度が変化した場合、新たなケアプランの見直しを行うこともあります。
三か月という枠は、利用者や家族が次のステップを計画するための目安にもなっています。
有料老人ホームへの移行プロセス
リハビリを重視した老健での滞在を終え、長期的な住まいとして有料老人ホームへの移行を考えるケースは少なくありません。
ここでは移行までの流れを以下の4つの順番で分かりやすく解説します。
1.退去計画
2.施設見学と情報収集
3.退去手続きと入居手続きの進行
4.引っ越しの準備
1.退所計画
介護老人保健施設でのリハビリが終了し、医師やケアマネジャーと相談して、在宅復帰が難しい場合や長期的な住まいが必要と判断される段階です。
次のステップとして有料老人ホームが適切かどうかの確認を行います。
2.施設見学と情報収集
介護付き有料老人ホームや住宅型、健康型などの種類を検討し、希望する住環境に合った施設を選びましょう。
事前に見学や説明会に参加し入居者のニーズに合った施設を探すため、情報収集は欠かせません。
施設見学が難しい場合はパンフレットの取り寄せや紹介会社に相談することもおすすめです。
3.退去手続きと入居手続きの進行
介護老人保健施設を退所する際には、事前に手続きが必要です。
通常は1〜3ヶ月前に退所希望を伝え、退去に関わる費用の確認を行いましょう。
そして、次の施設での契約手続きを進めていきます。
費用やサービス内容、入居条件を確認しておくことが重要です。
4.引っ越しの準備
本人と荷物を移動する手段を計画を行います。
自家用車での移動が難しいようであれば、介護タクシーの手配を行いましょう。
荷物の搬入も引っ越し業者の手配が必要であるのかなども、事前に確認もしておくと段取りがスムーズです。
また、次の施設へ荷物搬入する際は事前に搬入日を連絡しておくとトラブル防止にもなります。
移行時に確認しておきたいポイント
移行時には計画的な準備といくつかの注意点が伴います。
・ケアマネージャーへの相談
・行政関連の手続き
・退去手続きの確認
・施設選びのポイント
・家族間の連携
それぞれについて解説していきます。
ケアマネジャーへの相談
ケアマネジャーは、ご本人の状態や希望を元に、最適な施設やサービスを調整してくれる存在です。
相談する具体的な内容のポイントを3つ抑えておきましょう。
1.移行の理由と希望を明確に伝える 移行の背景や希望するサービス(リハビリ、医療ケア、食事支援、自由度など)を具体的に伝えましょう。
どんな施設で生活したいのか、具体的なイメージを共有することが円滑なサービス選定に繋がります。
2.医療面や健康状態に関する詳細を共有する 現在の医療ニーズ(投薬、通院、特別なケアが必要な病状)をしっかり伝え、どの施設が最適かをケアマネジャーと共に検討。
特に、医療面でのサポート体制(看護師常駐、訪問医療など)を確認し、必要な支援が受けられるかをチェックすることが重要です。
3.介護プランの見直し 介護サービスの内容が変わる可能性があります。
新しい環境に合わせて、介護プランを見直し、最適な支援が継続的に受けられるようにすることが大切です。
行政関連の手続き
- 介護度の確認
有料老人ホームに入居するには、介護度の評価が重要です。
介護度によって受けられるサービスや施設の選択肢が異なります。
自治体による「介護認定」を受けることが必要です。 - 経済面の確認
有料老人ホームは基本的に民間運営であり、料金体系も施設によって異なります。
生活保護を受けている場合や経済的に困難な場合、行政による支援を受けることができる場合があります。移行を考える際には、ケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉事務所など、行政のサポートを積極的に活用することが重要です。
退去手続きの確認
施設側に退去を希望する旨を正式に伝える必要があります。
施設に退去届を提出する際、退去日や理由、引き継ぎ事項について記載する必要があります。
- 未払いの料金や費用の精算
退去前には、老健施設に対して未払いの利用料金やその他の費用(医療費、差額ベッド代など)がないかを確認します。
また、退去時に追加で発生する費用についても把握しておく必要があります。 - 返金や保証金の返還
施設によっては、保証金が預けられている場合があります。
退去時にこれを返還してもらう手続きを行います。
この際、施設の契約書に記載されている返還条件を確認しておきましょう。
家族間の連携
有料老人ホームへの移行は、本人にとっても生活の質や安心感を大きく左右する転機です。
この過程では、家族間の連携が重要となります。
入居後も本人が安心して生活できる環境を整えるためには、家族間での情報共有や協力体制の確立、スムーズな移行をサポートすることが大切です。
以下の2つのポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 家族間での情報共有
本人の希望を尊重しつつ、家族全員が同じ方向を向いて協力する。
家族間での認識のズレを防ぐために、どのように意見交換を行うべきか話し合う時間を設けましょう。
また、入居後に新たな問題が発生した場合、家族内での相談やサポート体制も大事です。
たとえば、仕事で長期不在の場合や家庭環境などで施設と連絡が取りにくい状況もあります。その際に、家族間での連携が取れていると施設との連絡が滞ることなく、本人にとっても安心できる新しい生活を作り上げることができます。
また、一人だけが抱え込んでしまうと負担も大きくなるため、協力することが大切です。
- 本人の意向を尊重する
可能であれば、本人の希望や不安を事前に聞き、移行に対して本人の心構えを整える。
有料老人ホーム以外の選択肢
次の住まいを選ぶ際には有料老人ホーム以外にも様々な選択肢があります。
その人の介護度や生活スタイルによって、選択は異なります。
以下では、有料老人ホーム以外の選択肢として4つを紹介していきます。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・グループホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・在宅復帰
ご参考下さい。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護が必要な高齢者が、数日から数週間ほど施設に宿泊して介護サービスを受けられる制度です。
たとえば、介護が必要な家族と同居している場合、旅行などで家を空けることになり、一時的に介護が難しくなるときに利用することができます。
介護者の負担を軽減する介護者の休息でもあるため、上手く活用して、無理のない介護生活を続けることが大事です。
グループホーム
認知症の高齢者が少人数(5~9名)で共同生活を送りながら、介護スタッフの支援を受ける住まいです。
家庭的な雰囲気の中で、できる限り自分でできることは自分で行い、生活の中での自立支援を重視しています。
料理や洗濯、掃除などの日常生活をスタッフと一緒に行うことで、認知症の進行をゆるやかにしたり、安心感や自己肯定感を保てる環境が整っています。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
バリアフリー対応の賃貸住宅に、見守りサービスや生活支援が組み合わさった高齢者向けの住まいです。
比較的元気な高齢者や、軽度の介護が必要な方が対象になります。
スタッフが常駐し、安否確認や緊急対応などの基本サービスが提供されるため、一人暮らしでも安心です。
また、施設によっては、食事の提供や医療機関との連携、リハビリやレクリエーションが用意されているところもあり、暮らしやすい環境です。
ただし、介護度が高くなった場合や、医療的ケアが必要になったときには、別の施設への移動を検討する必要がある点も知っておきましょう。
在宅復帰
自宅復帰に向けた準備には、身体の機能改善だけでなく、自宅での生活をスムーズに送るための環境整備も重要です。
自宅での介護方法や心構えを学び、一緒に考えながら進めることで、利用者の生活の質を高めることができます。
特に着替え、食事などの生活動作の練習やオムツ交換、移乗、家族への介護指導。また、手すりの設置、階段の改善など家の環境確認を行うことが必要です。
事前に施設の職員へ相談することをおすすめします。
そして、自宅復帰後も介護保険サービス(訪問介護、訪問リハビリ、デイサービスなど)を活用することで、無理なく自宅生活を続けることが可能です。
自宅へ戻ることは、ゴールではなく新しい生活のスタートです。
準備を把握しておくことで、安心してわが家での暮らしを再スタートすることができます。
まとめ
介護老人保健から有料老人ホームへの移行は、「リハビリのための場所」から「暮らすための場所」への転換を意味します。
どの施設を選ぶかによって、本人の生活の質が大きく左右されます。
不安を感じる方も多いからこそ、情報を集め、本人と家族が納得して決めることが何よりも大切です。
このコラムを読むことで「その人らしく生きること」を第一に考えた住まい選びができる、ヒントとしてこのコラムがお役に立てれば幸いです。